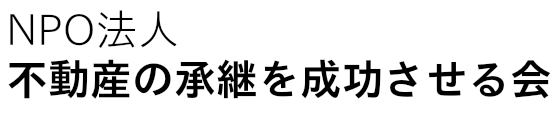第18回講演のまとめ 梶田光太郎先生 #土地家屋調査士 #建築士 #M&A
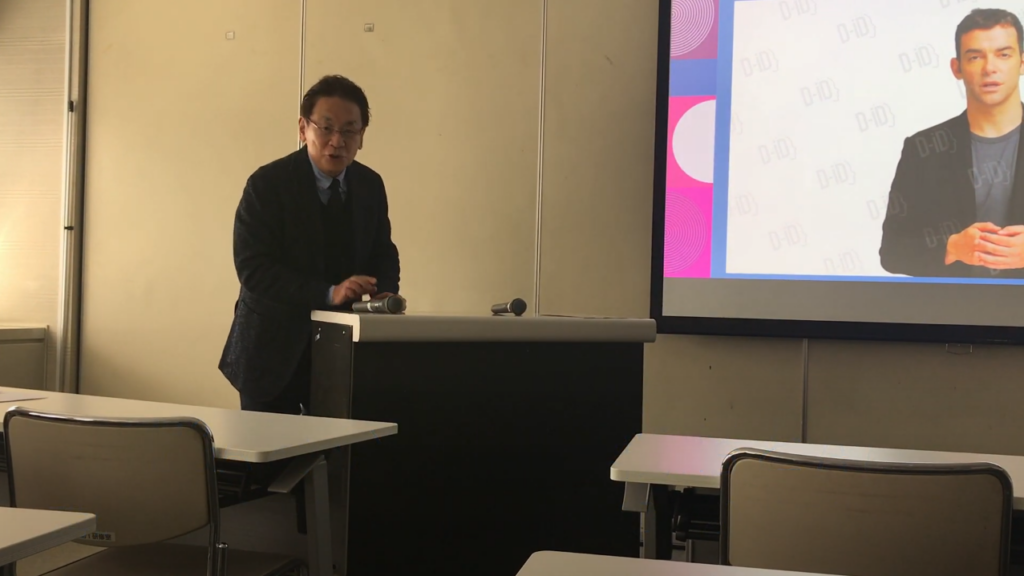
Table of Contents
テーマ
人口減少と高齢化が進む日本において、中小企業の生き残りのためにM&Aは重要な戦略となっています。AIの活用や他企業との協力も含め、企業の持続性と成長を確保するための多角的なアプローチが必要です。
要点
1. M&Aは中小企業の事業承継や成長戦略として重要性を増している
2. 2024年のM&A件数は過去最多の4700件を記録し、中小企業が70%を占めた
3. AIの発展が人手不足を補う一方で、新たな課題も生み出している
4. M&A実施には約1年から1年半の期間がかかり、秘密保持が重要
5. 国は事業承継・引継ぎ補助金制度を設け、M&Aの仲介費用の一部を補助している
6. 企業の生産性と持続性確保のために、複数企業の協力による相乗効果が重要
7. 2025年5月から宅地造成および特定盛土等規制法の運用が開始される
ハイライト
“M&Aという経営戦略とAI、すごく興味があります。皆さん楽しみにしてくださいね。”– 竹本弘司 《セミナー開会の挨拶》
“人口減少イコール労働者人口の減少ですから、こういったAIっていうのもそのどんどん進化してて、その人手不足を補っている。”– 《講演者の発言》
“経営戦略とすればM&Aしかないと僕は個人的には思うんですけど、あの、まあそういう時代がぼちぼち来てるんじゃないのかな。”– 講演者
“契約の内容が曖昧だったっていう可能性も考えられるんですけど、ここは十分に約束をそのプロの間に立ってもらって、きちんと確認して、約束ことを履行してもらわないと、こういうトラブルになってしまうという。”– 講演者
“国もM&Aを推奨していると。こういった中小企業の支援を真剣に考えている。それは労働の場を失わないこと、産業を失いこと、失わないこと、技術を失わないことを真剣に取り組んでいるという、そういう表れだと思っています。”– 講演者
“後継者不足も含め、中小企業350万社には生きの声をかけた戦略が求められます。”– 講演者
“企業のその生産、あるいはあの持続性というのは、やっぱりもっともっとその命に関わることなので、真剣に考えていかなきゃいけないんじゃないでしょうか”
“経営戦略として、先が見通せる可能性が出てくるっていう手段として、M&Aはよっぽどまあ、これからの時代いいんじゃないのかなっていう。”
“これからは、土のことを触る場合、この盛土法にかかるんだぞっていうことをちょっと覚えといていただけると、タイムスケジュールや作業のそのまあバランスなんかを考慮する上で、あの参考になるのかなと思います”
章とトピック
1. 経営戦略としてのM&A
M&Aは現代の経営戦略として重要性を増しており、企業の生き残りや技術・雇用の維持に貢献している。2024年には日本企業のM&A件数が過去最多の4700件を記録し、その中で中小企業が70%を占めている。しかし、後継者不足の問題も深刻で、約250万件の中小企業が後継者不在の状態にある。
M&Aは企業の救済や立て直しから、中小企業の生き残り、雇用保護、技術維持へと目的が変化している
人口減少と労働力不足がM&Aの必要性を高めている
AIの発展が人手不足を補う一方で、新たな課題も生み出している
2024年のM&A件数は4700件で過去最多を更新し、中小企業が70%を占めている
2. 事業承継の現状と課題
2025年2月22日の時点で、事業承継に関する相談件数が過去最多の4700件を更新した。親族内承継や社内承継には課題があり、M&Aによる事業承継が増加傾向にある。
親族内承継は子供の能力と経営意欲が必要
社内承継は社員の責任負担能力が課題
M&Aは幅広く承継先を探せるが、交渉が難しい
3. M&Aの実施とトラブル事例
M&Aの実施には様々なトラブルリスクがあり、適切な仲介者と契約内容の確認が重要である。各都道府県に設置された事業承継・引継ぎ支援センターが相談窓口となっている。
財務状況や経営者保証の扱いが曖昧な場合にトラブルが発生
支払い条件や雇用維持の約束が守られないケースがある
事業承継・引継ぎ支援センターが相談窓口として機能
4. M&Aの流れと補助金制度
M&Aの実施には約1年から1年半の期間がかかり、秘密保持が重要。国は事業承継・引継ぎ補助金制度を設け、M&Aの仲介費用の一部を補助している。
M&Aの準備から成立まで1年から1年半かかる
風評被害を避けるため秘密保持が重要
国の補助金制度でM&A仲介費用の一部が補助される
5. 中小企業の生き残り戦略としてのM&A
少子高齢化や生産年齢人口の減少により、中小企業の数が年間約7万社減少している。DX化は避けられず、中小企業には生き残りをかけた戦略が求められている。
生産年齢人口が年間約75万人減少
中小企業数が年間約7万社減少
雇用が大手企業に偏る傾向
6. 企業の持続性と成長戦略
企業の生産性と持続性を確保するために、複数の企業が協力して相乗効果を生み出すことが重要である。NPOのような組織でも、異なる資格や資源を持つ人々が集まることで、情報や人脈を共有し、企業にとってプラスになる可能性がある。
企業の生き残りと成長のために、複数の企業が協力して相乗効果を生み出すことが必要である
NPOのような組織では、異なる資格や資源を持つ人々が集まることで情報や人脈を共有できる
企業の生産性と持続性は命に関わる重要な問題であり、真剣に考える必要がある
7. M&A(合併・買収)の実践と課題
講演者は自社のM&A経験を共有し、2022年から2025年2月22日までの過程を説明した。社内承継から始まり、最終的にIT企業とのM&Aを選択。株式譲渡後も代表者として残り、相乗効果を目指している。課題として人材不足や社員の退職リスクがあるが、新たな可能性も見えてきている。
2022年に事業承継について支援センターに相談し、当初は社内承継を選択
2023年5月にM&Aへの切り替えを決定
2024年9月に株式譲渡、10月に社内発表
IT企業との統合により、公共土木分野への進出が可能に
M&A後の課題として社員の退職リスクや人材不足がある
8. 宅地造成および特定盛土等規制法の運用開始
2025年5月19日から名古屋市において宅地造成および特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用が開始される。この法律は熱海の土砂災害を教訓に制定され、造成工事や土地の改変に関する規制を強化する。
2025年5月19日から名古屋市で運用開始
造成土の移動や地形の改変を行う際に規制の対象となる
熱海の土砂災害を教訓に制定された法律
提案
AIと経営戦略、および不動産関連の専門知識を組み合わせた新しい視点での議論が期待される
M&Aを検討する際は、専門の仲介者に相談することが重要
AIの活用とM&Aを組み合わせた戦略を検討すべき
事業承継方法の選択には、経営能力と責任負担能力を重視すべき
M&A実施時は専門家の助言を受け、契約内容を慎重に確認すべき
M&A実施を検討する際は、事業承継・引継ぎ支援センターに相談することが有効
技術革新や需要に合った製品開発など、生き残りをかけた戦略が必要
企業の持続性を確保するために、他社との協力や情報共有を積極的に検討する
AI提案
– この授業の核心は、M&A(合併・買収)と事業承継の理解です。M&Aの事例研究を通じて、その戦略的重要性と実施プロセスを把握することをお勧めします。
– M&A(合併・買収)の核心内容:
企業成長のための効果的な戦略
リソースや規模の拡大、新分野への短期間での進出が可能
事業承継の選択肢の一つとして重要性が増している
準備から成立まで1年から1年半かかり、秘密保持が重要